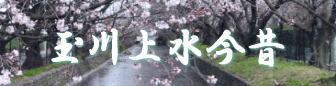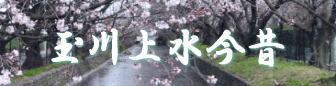取水口 投渡堰 第一水門 小吐口
|
 |
明治末年頃
|
 |
| 1990年代 |
|
対岸からS字型に大きくカーブして羽村岸に突進してくる多摩川本流をせき止め、堰とほぼ直角に設けた第一水門から取水して、余分な水は小吐水門に設けた口から本流に戻しながら第二水門で水量を調節して玉川上水に送っている。
この羽村堰と取水口の仕組みは玉川兄弟が江戸・承応3(1654) に玉川上水を開削した当時と余り変わらず、寛政年間(1789〜1801)にはほぼ現在と同じ構造になっていたという。
堰には太い支柱(固定堰)を設け、支柱と支柱の間に渡した桁で1メートル間隔に立てた松の丸太を支えている。
丸太と丸太の間には粗朶や木の皮を束ねたもの、砂利などを使って水を穏やかに堰き止めている。
一滴の水も漏らさず…というのではなくアバウトに、しかも大水が出た時は桁をはずして丸太などの堰を投げ払うことから投渡堰(なげわたしせき)と称されている。
水の勢いで固定堰や取水門が壊されるの最小限に食い止め、送水がストップするのを防いでいる。水の破壊力を知り尽くし逆らわない知恵を生かした堰の構造で、全国でも珍しく貴重な存在である。
平常時と大出水時の投渡堰 |
マップ参照
|