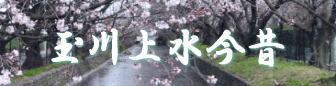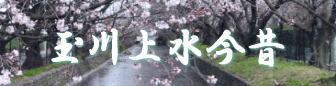砂川分水口の付け替えと旧水路
|
 |
昭和47年当時
|
 |
旧砂川分水の堀2006年現在
|
|
江戸開幕から6年後、狭山丘陵の麓・岸郷出身の三右衛門の願い出によって慶長14年(1609)に始まったとされる砂川新田開拓は、その後明暦3年(1657)玉川上水からの分水が許可されることによって徐々に進展。
江戸中期には砂川村として、五日市街道に面し東西4キロほどの典型的な街村を整えた。
玉川上水の沿革を知る上での基本資料とされる『上水記』絵図には、当初の砂川分水口は五日市橋(現天王橋)下手に描かれている。
その後、明治政府の代になって許可された玉川上水通船に伴い、航行をスムーズにするため流域の分水口の付け替えや統合が行われた。
砂川分水も明治3年(1870)、それまでより上流の松中橋下流に分水口を設けて、上水と平行した新しく水路が堀りかえられた。
その半間幅ほどの水路は現在も松中橋下流から約300メートル開渠で現存しており、せせらぎに沿った緑道も整備され、武蔵野の面影を留めている。 |
 |
| 砂川分水旧水路に沿った緑道 |
マップ参照
|