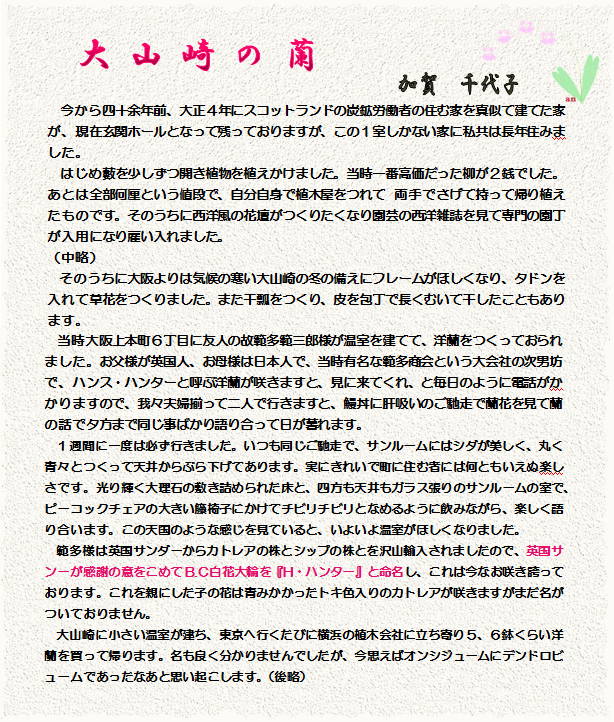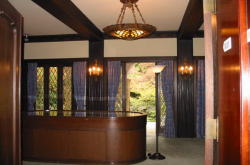大阪駅または京都駅からJR京都線(在来線)で約30分
大山崎駅からなだらかな坂道を歩いて10分ほど。木津、
宇治、桂の三川が合流する天王山麓を切り拓いて、加
賀正太郎が週末を過ごす山荘づくりに取り掛かったのは
大正3~4年。100年近くも前のことです。
英国遊学中にウィンザー城から眺めたテ‐ムズ河畔のラン
ドスケープに似たこの大山崎の地を選んだそうです。
|
 |
|
建築当初とほぼ同じ状態の
『悠々居』と称された本館 |
山麓にさしかかると巨大な岩の洞穴を潜り抜けるようにして
進んだ先に、明るい色の西洋瓦をあしらった開放的な表門
があり、早々から心憎い演出。この年は全国的に紅葉はイ
マイチでしたが、 大山崎山荘の楓は常緑樹の間で一本一
本微妙な紅葉が楽しめました。
|

一木一石に至るまで加賀正太
郎の美意識が感じられる表門 |
大山崎山荘の建築当初の建物についてはアサヒビール・大
山崎山荘美術館のホームページや加賀千代子夫人の随
想でも語られているように、スコットランドの炭鉱労働者住
宅がモデルになっているのに対して、英国人の血を引くハン
ス・ハンターが後年昭和13年前後に小平に設けた範多邸
は那須塩原の庄屋を移築して純和風の造りでした。
しかし、柱や梁の1本1本にもこだわって美意識を追求して
いる点に関して、正太郎とハンス・ハンターには共通する部
分が多いと感じられました。
ハンス・ハンターもかつて大山崎山荘を訪れ、参考にした点
が多いのではないでしょうか。 右の2点は大山崎山荘と範
多邸の天井部分で、和洋の違いを超えて木組みの精巧さ
や美がたくみに生かされています。
|
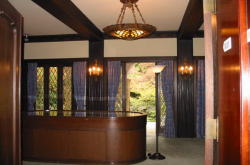 |
大山崎山荘本館1階ホールの
吹き抜け
|
 |
| 小平・範多邸座敷の照明と天井 |
|
大山崎山荘が位置する天王山麓は、天正10(1582)羽柴秀吉と明智光秀の
山崎の戦いで知られる天王山の南麓で、木津川と宇治川、桂川が合流して淀
川となる地点です。 |
|
在りし日の姿を求めて ⑪