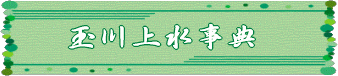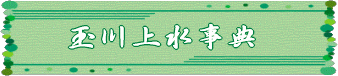|
明治2年(1869)9月、玉川上水を利用して物産を輸送しよう
と、多摩郡の羽村・福生村・砂川村の名主3人が通船事業の
請願を出した。翌年4月に認可される。それまでは、馬の背
に振り分けて荷物を運んだでいたのが、一度に大量に運搬で
きるようになった。
船は長さ6間(10.8㍍)、幅5尺(1.65㍍) までとされ、木造
平底。商用や東京見物の旅客も運んだ。桜の季節には舟の中
から小金井桜の花見もできた。船を停泊させ荷物や人の揚げ
降ろしをする船溜りが要所要所に設けられ、船を曳いて上流
へあげるために両岸に舟曳き道もつくられた。
1艘の積載能力は約2㌧。月に6往復し、最盛期の明治4年
10月には104艘の船があった。「16~17 里の船賃より1里の
(馬による)駄賃の方が倍もする」といわれ、運賃は格段に割
安となった。
このため、甲州や信州の物産、たばこ・ぶどう・繭蚕糸・紙
・茶などが東京に移出され、玉川上水沿岸の村々からは野菜
・薪炭・酒・織物(八王子産)などが東京市中へ運ばれ、逆に
東京からは米・塩・魚類などがもたらされた。
しかし、玉川上水は東京の市中に飲用水を供給する水路であ
る。民部省土木司、大蔵省土木寮が所管していた期間は、通
船は許可されていたものの、玉川上水が東京府に移管される
と、「上水不潔ニ至り」として、明治5年5月30日に停止。
根強い再興運動も効なく、やがて船溜りは埋立てられてしま
った。
|