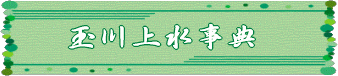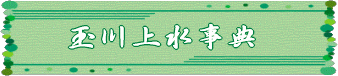|
明治31年(1898)淀橋浄水場の竣工・通水によって近代水道によ
る給水が始まったが、 同40年の東京市の給水人口は約101万人
だったのが、5年後には150万人に迫る。 玉川上水の自然流下
に頼るだけでは需要に追いつかず、明治44年から貯水池建設が
計画された。
大正5年(1916) 狭山丘陵にアースダム工事が開始。村山貯水池
(多摩湖)上貯水池の湖水面積は 約40・6㌶、下貯水池110・8
㌶、山口貯水池(狭山湖)は 189・3㌶で三貯水池を合わせた有
効貯水量は3435万立方㍍。
村山下貯水池が完成したのは大正13年、上貯水池は昭和2年に
山口貯水池は昭和9年に竣工した。
これらのダム建設で石器時代から集落のあった宅部、内堀など
7カ村161戸が土地を追われたが、これらのダム建設工事中に、
新に小河内ダムを計画しなければ追いつかないほど東京の水事
情は逼迫していた。
羽村取水所第三水門から地下の導水管(羽村村山線)を通して村
山貯水池へ、山口貯水池へは小作取水所からの導水管(山口線)
で水が送られている。
三貯水池に貯えられた水は東村山浄水場と境浄水場に送られて
いるが、利根川水系の朝霞浄水場と導水管で連結されており、
相互送水できる。村山貯水池は平成22年まで耐震工事中。
|