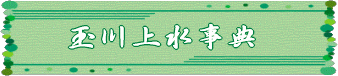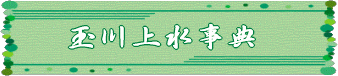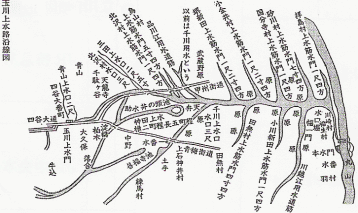|
持ち場村は上水の沿岸村々に持場が割当てられ、草刈・汚染防
止・高札。分水口を保全する負担を負わされていた。玉川上水
では、取水口の羽村から四ッ谷大木戸手前の天竜寺門前までの
村々である。
該当する村は、右岸と左岸にそれぞれ23ヵ村であった。両岸が
長い砂川村 8543㍍、小川村8145㍍、最短は久我山村の380㍍で
ある。
長いと、特に隔年一斉の草刈時に重い負担を村民に負わせるこ
ととなる。上水方役人の通行や見廻りに支障のないよう通路の
草刈も実施することになっていた。更に一方では、刈り取った
草は大切な肥料代として草野銭を納入しなければならなかった。
中期以降、ヌカの使用により草の肥料価値が減少したとはいえ、
草刈作業の負担は大変大きいものである。
岸にたれた草、屹立した岸、落ちると這い上がる術のない草刈
は、人々を呑みこんだ事件もあることから別名「人喰い川」と
呼ばれていた。筏を組みそれに乗り、下から刈り取る作業は予
想以上に人手と日数を要し、危険を伴う作業を強いられたので
ある。すべてはボランティアであった。
文書によると3ヵ村で 延べ700人との記録があり、この期間中に代田
村の芥留で揚がるゴミの量が急増するする関係上、各村々では
付届けをしなければならなかったのである。
|
 |
持ち場村によってきれいに草刈さ
れていた明治時代の小金井堤 |
 |
明治元年の玉川上水
堀越正雄著『水道の文化史』
より |
|