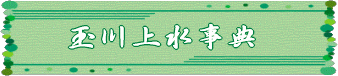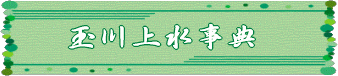|
玉川上水に通船を試みたのは、明治3年(1870)4月15日。通船は
その後、明治5年(1872)5月31日の通船禁止までの僅か2年間で
はあったが、通船のための船着場(物揚場)のことを「船溜」と
いう。
長短はあるが、船溜の平均の長さ15間(27.3㍍)、土手にくい込み
川幅を3間(5.5㍍)拡幅した。
「船溜」のことを営業形態から「河岸」或いは「問屋」と称した
のである。物揚場は5間(9㍍)、幅2間半(4.5㍍)。
明治当初、羽村・砂川の2ヵ所、四ッ谷人大木戸1ヵ所をはじめ
4月以降は全域に許可され(羽村~四ッ谷大木戸)船溜と物揚場
・河岸問屋の数は32ヵ所であった。そのうち小平市域は7ヵ所で
ある。
現在、唯一原形に近い形を留めているのは久右衛門橋左岸下流北
詰に法面がだれて後退している場所である。土留のため、松杭の
間隔は約60㌢、杭列は東西方向で上下3段 計10本残存している。
この場所は、明治5年(1872)5月まで小川村荒井清五郎が久保河
岸として経営していた。
一斉に埋め立て工事の着工は、明治8年(1875)8月以降である。
なお、大正5年(1916)作成の玉川上水路の実測図には幅6㍍の淀
みが記載されており、再度埋立てたものとみられる。現状のまま
に船溜の遺構として、或いは産業遺跡として残したいものである。
|