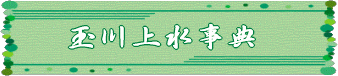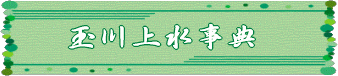|
江戸表から水元取締役として侍が執務するための詰め所が上陣屋
である。台風時、非常時の増員、突発事故時の緊急処置。早馬で
江戸表に注進し、上司の指示を仰ぐことになっている。
水道局資料にみる羽村旧陣屋図によれば、玄関・仲の間・詰所・
次の間・上の間の部屋が一体となっており、勝手と道具置場と筵
置場があった。
明和5年(1768)から上水係が江戸町奉行から普請奉行に代わるが、
日常は江戸から出向の水番人の指南役。当初は坂本家が陣屋構内
にある水番人小屋に居住していた。これを帳場と呼んでいた。
指田家は、自前の家があっての水番人であったため、居住はして
いない。
水番人の仕事は役人の出迎え、分水口の開閉、普請の際、出役の
指図、普請修復仕様注文書、それによる入札等、上水普請・筏通
場修復を請負うことになり、工事用の資材である蛇篭と枠組とそ
れの詰石や筵、そだ、俵、松明等の保管場所でもあった水番人小
屋では手狭になったため、享和2年(1802)6代目の指田茂十郎は
許可を得て陣屋の外に陣屋を造ったため、指田家を「下陣屋」と
呼ぶ。その跡地は、社会法人玉水学園のある場所である。
昭和45年(1970)まで、羽村堰の廃材で造ったといわれる陣屋門が
残っていた。
|